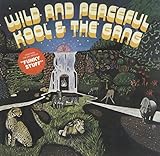グレイトフル・デッドの起源
[67年]シスコ、ゴールデン・ゲイト公園で行われたヒューマン・ビーイン
(略)
「みんなでアシッド・サーカスのバスに乗りこんだ。そして、そこで常識や慣習にとらわれない未知の領域、自由でいるってどういうことかを探した。それが僕たちの始まりだね」(略)
[2016年ボブ・ウィアーは]筆者とのインタビューで、デッドの起源を語ってくれた。「リーダーも作らない、ルールもいらない。とパンクでアナーキーな態度で、自分たちの本当にやりたいことを探していたのさ」
そんな彼らを“発見”して、声をかけたのが新進作家ケン・キージーと彼のまわりに集まっていた元祖ヒッピー集団、メリー・プランクスターズ(陽気ないたずら者たち)。今はアメリカの文化遺産としてスミソニアン博物館に展示されている、原色の蛍光ペイントで塗りたくられた改造スクールバス、ファーザー(より遠くへ)号に乗ってカリフォルニア各地で、まだ合法だったLSD入りのパンチを採る意識拡大実験パーティ、アシッド・テストを催していた。
そのパーティに参加してハウスバンドのように演奏しているうちに「混沌の中から自然に新しい秩序が生まれてくることがわかった!」とジェリー・ガルシア。それがデッドの音楽的探究、ダイナミックなグループ・アイデンティティの基盤になった。たくさんのコードを知らないことを逆手に、ひとつのキーでモーダル音階を延々と続けるうちに、彼らは“サイケデリック・サウンド”と呼ばれる自分たちのスタイルを見つけたのだった。
(略)
ウィアーは答えてくれた。「でも実際のところ、もう、あの集まりの時には僕にとってピークは終わっていたね。集まった人数の多さをことさら強調したり、サイケデリックをやっている人たちに声高に語りかけ、どこかに導こうとするLSDスポークスマンもいやだったね。それまでの僕らのパーティはみんなひとりひとりが自分の何かを持ってきていたんだ。タイダイの布や服、スタンリー・マウスやアルトン・ケリーのようなユニークなポスター・アートの連中。でもビーインの頃は何も持たず、ただパーティに来たくて来るだけの連中が増えてきた。ああ、ヒッピー・ドリームはこれで終わりかなって感じた。それから音楽に集中して、長く不思議な旅を始めたのさ」
きみはどっちの側の人間だ?
1967年のロック音楽文化の発展に寄与した功労賞なんてものがあったとしたら、それはまちがいなく25才のこのリヴァプール出身の若者に贈られたことだろう。イギリスで保守的な支配層から、若者に蔓延する麻薬撲滅の動きがひそかに始まり(略)
麻薬常用シンガー(らしい)として最初の標的にしたのがフォーク・シンガー、ドノヴァン。ポールは早速、新作「メロー・イエロー」録音中のスタジオに出かけ、タイトルソングのバックヴォーカルに加わったり、別の曲でベースを弾いたりして友情を表明。
これは乾燥させたバナナの皮を吸うと合法的なハイ状態が得られる、と当時、世界中で流布した噂とシンクロして、アメリカではチャート2位の大ヒットになったが、どちらも違った。ドノヴァンが歌ったのは女性をめろめろにするヴァイブレイターのことだったし、バナナの皮の乾燥はいくら吸ってもハイにはならない。
(略)
[タレコミによりキース・リチャーズを張り込んだ警察は、ジョージ・ハリスン夫妻が帰宅するのを見届けガサ入れし、ミック、キースらを逮捕]
ワールド紙は実名入りで、裸だったマリアンヌと麻薬で乱交パーティをしていたかのように書き立てていた。
(略)
捜索を指揮した巡査部長、ノーマン・ピルチャー[は](略)
翌年ジョン・レノンを逮捕。その名は(略)「アイ・アム・ザ・ウォルラス」の中でセモリナ・ピルチャードとされ、ビートルズの歴史に名をとどめている。
(略)
[『サージェント・ペパーズ』発売]
多くのヒップな若者たちには、解読なんて少しも必要なかった。ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウイズ・ダイアモンズ……3つの頭文字を並べれば、L…S…D…。メッセージは明快だった。“きみも旅立つといいのに”(略)
「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」。“アイ・ラヴ・トゥ・ターン・ユー・オン……” ターン・オンとはドラッグでストーンすること、意識の新しいスイッチをいれるという意味の言葉だ。インド旅行から帰ってきたジョージ・ハリソンがインドの民俗楽器シタールを取り入れて“きみはどっちの側の人間だ?”と精神世界への旅を示唆するように歌っていた「ウイジン・ユー、ウイズアウト・ユー」も、多くのリスナーの心の扉をノックした。
モンタレー・ポップ・フェスティバルの舞台裏
「“なんでジャズやフォークのフェスティバルはあるのに、ポップ・フェスティバルはないんだ? シスコ、ロスのミュージシャンで集まり、西海岸でも俺たちで大きな集まりをやろうぜ!”、アラン・パリザーの家でモンタレー・ジャズを観に行った帰りにそんなお喋りをしていたんだ」(略)スティーヴン・スティルスは言っていた。
アラン・パリザーは製紙業で成功した一族に生まれ、それまでいくつかのロックイベントを企画して成功させ、ビートルズのリンゴ・スターを腹心の友としてロサンジェルスの“ハイ・ソサエティ”でもよく知られた若者だった。彼が主催したイベントでMCをやって仲良しになったのが、バーズのパブリシストとなり、イギリスから家族とともに引っ越してきてこの町で活動していたデレク・テイラーだ。「次の日すぐ、アランから電話があり、これからデレクとプロモーターのベニー・シャピロに会いに行くから、一緒に来て是非、昨日のアイディアを彼に話してきかせてやってくれよ、と言うんだ」とスティルス。
こうしてシャピロはすぐにこのプロジェクトのパートナーとなり、インドのラヴィ・シャンカールを$3000の出演料でフェスへの参加をとりつけた。一方、パリザーはモンタレーに23ヘクタールの会場予定地をおさえると、資金作りに奔走し、シスコ・シーンのビッグガイ、ビル・グラハムから名前を出さないという条件で1万ドル、家族と自分の銀行口座3万ドル、計6万ドルの活動資金を捻出した。そしてフェスの看板となるメイン・アクトとして当時、「夢のカリフォルニア」の大ヒットで爆発的人気のママズ&パパスに白羽の矢をたてた。出演の依頼がてら、膨大な金額となるだろう出演料をどうやって工面したらいいかを相談しにダンヒル・レコードのルー・アドラーとジョン・フィリップスを訪ねたのだった。
「ここでハリウッドならではの宮廷乗っ取り事件が起こったのだ」と最初からの一部始終を知るテイラーはその名著「サイケデリック・シンドローム」(原題・It was 20 Years Ago Today)で少し苦しげに告白している。
何が起きたかというと、$5000の出演依頼にアドラーとフィリップスはのらなかったが、ポップ・フェスティバルの計画には大乗り気。チャリティ・イベントにすれば出演料をカットできるといいながら、いつのまにか逆に$5万でアイディアもろともシャピロの“買い取り”をし、最初の企画創案者パリザーからすべてのコントロールを奪ったのだ。
早速ビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソンに“チャリティ・フェスティバル”への出演を打診すると、夏に“究極のティーンエイジ・シンフォニー・アルバム” 「スマイル」を完成して発売する予定だったブライアンは、絶好のプロモーションになると思ったのだろう、実行委員会に名前を載せることもふくめて快諾してくれた。
ポール・サイモンも「グルーヴィー!(ごきげんだね)」と参加を表明(略)
ビートル・ポール、ミック・ジャガーが「素晴らしいじゃないか」と実行委員名簿リスト入りを承諾して、ドミノ倒し。
(略)
業界の動向に敏感なプロデューサー、アドラーはフェスティバルの成功の鍵は多くの若い一般の音楽ファンたちの信頼を得ること、それには今、話題のサンフランシスコ・グループの参加が不可欠だと感じていた。こうして、サンフランシスコに飛び、町の高級ホテル、フェアモント・ホテルでフィリップスとアドラーはジェファーソン・エアプレイン、グレイトフル・デッドらのメンバー、それに彼らの良き理解者であるサンフランシスコ・クロニクル紙のジャズ評論家、ラルフ・グリースンをオブザーバーに、最初のミーティングを行った。しかし、シスコ・グループは
(略)
アドラーの話が終わると“甘い話で釣って儲けようって魂胆だろう”、“俺たちの人気に便乗して、出演するロスのバンドの評判をあげようってわけだ”、“入場料はタダにすべきだ!”と一斉に攻撃と反論のつぶて。
「あともう少しで殴り合いになるところだった」とアドラーは後にため息まじりで回想している。洋服屋で仕立てた高級なスーツ姿のアドラーは“ビジネスしか頭にないスクエア野郎”、あの“くそいまいましいシスコを利用した人工甘味料入りの曲(「花のサンフランシスコ」)をでっち上げた”フィリップスは“コマーシャルに身売りした情けないフォーク野郎”とデッドのマネージャー、ロック・スカリーの目には映った(と彼は後の回想録に書いている)。
(略)
アドラーとフィリップスはすごすごとロスに帰っていった。
シスコ・グループを説得してフェスティバルに参加するようにしむけたのは、これまで数多くのジャズ・フェスティバルを経験して、そのメリットを熟知していた、この年20歳のベテラン音楽評論家、ラルフ・グリーソン(略)
さらに調停役として、一役かったのは、“片足をヒッピー界に、だがもう片足はしっかりビジネス・ワールドに”をワーキング・モットーにしていたフィルモアのプロモーター、ビル・グラハムだった。
「どの出演者もノーギャラでの出演依頼に首を振らなかったのには、本当にびっくりした」とアドラー。その分、エビや蟹、ワイン、シャンパン、美味しい食事を用意して、ていねいに心地よい最高のもてなしをするよう、アドラーたちにアドバイスしたのはグラハムだった。そして会場で、バックステージでいつも笑顔、気品ある態度でミュージシャンたち、世界中からやってきたプレス関係者(その数1100人)を出迎え、みんなから愛されたのは、あのビートルズ・ファミリーのひとり、デレク・テイラーだった。
ミュージシャンの中で、ほとんどただひとり、その呼び名 Cross のとおり、コンスタントにローレル・キャニオンとハイト=アシュベリーの間を行き来して、ロスとシスコ・シーンの架け橋をしていたのが、デヴィッド・クロスビーだ。
「クロスビーはいつ見てもまぶしいほどに発光している、カリフォルニア文化の申し子って感じだったよ」と当時まだ18才、オレンジ・カウンティ出身のサーフィン好きの駆け出し吟遊詩人、ジャクソン・ブラウンは言っていた。「シスコの仲間たちに金持ちって思われないように、わざわざワーゲンバスにポルシェのエンジンを積みかえて走っていたんだぜ。それこそ彼そのものじゃないかい──パワーのあるヒッピー!って(笑)」
「夏の野外コンサートといえば容赦なく照りつける太陽との戦いになるのに、モンタレーはまったく違っていた」
ジェファーソン・エアプレインのディーヴァ、グレース・スリックは後に自伝『サムバディ・トゥ・ラヴ』でこの時の会場の印象をこう記していた。
「大木の緑の枝が日射しを柔らかな光線に変え、あたりはまるでディズニー映画のシャーウッドの森のような、それは実に優しい風景だった」
メイン会場の裏には40人ほどのヒッピーが食べ物、手製のアクセサリーやジュエリーを売る出店が並び、少し未来的なデコレーションがほどこされた2番目に広いスペースには、会場の演奏の模様を巨大な白のキャンバス・スクリーンにビデオで投影するなど、どこにいても人々を和ませてくれる、視覚的なセッティングがなされていた。後で3日間の体験をエリック・バードンは「モンタレー」という曲にして、こう歌っていた。
ある者は聴きに、ある者は歌いに、またある者は花をあげにやって来た
若い神々は観客にほほえみかけ、生まれたての愛の音楽をかなで
子供たちは昼となく夜となく踊り続けていたよ、モンタレーで
バーズがエアプレインが空を飛び、ああ、ラヴィ・シャンカールが僕を泣かせた
ザ・フーは炎と光を炸裂させ、デッドは人々の度肝をぬき
ジミ・ヘンドリックスは世界を火にくべ、燃え上がらせたんだ
(略)
人生の真実を知りたいのなら、いいかい、音楽を聞きのがしてはいけない
3日間みんなで一緒になって動き、体揺らしながらわかりあったのさ
おまわりたちまでが、ぼくらと一緒になって楽しんでいたなんて信じられるかい
モンタレーで、モンタレーで、あの南の町、モンタレーで
あたりにはシャボン玉が飛び、どこにいてもマリファナの香りが漂っていたが、喧嘩もどんなぎも起こらず、ひとりの逮捕者も出なかった。地元の警察署長、フランク・マリネロは、会期前は懐疑的だったが、いざフェスが始まると若者たちのピースフルな様子に終始笑顔を浮かべ、部下たちの半数以上を帰してしまった。
「僕はヒッピーたちが好きになったよ。今度休暇になったらハイト=アシュベリーを訪ねてみよう。きっと友達になった連中にたくさん会えるだろう」
デレク・テイラーはその言葉をきくと、自分がしていたビーズの首飾りをはずし、彼の首にかけるとこう言った──「これで私たちは一緒になれましたね」
泣いていたのは金曜日の昼のジャニスひとりだけ。(略)自分のパフォーマンスがマネージャー、チェット・ヘルムズの頑強な反対のために一切撮影されていなかったことを知った時だった。大声を上げて泣きじゃくる彼女。(略)
ディランの敏腕マネージャー、アルバート・グロスマンの提案で[最終日に再出演することに]
(略)
[マイク・ラヴの猛反対で不参加となったブライアン・ウィルソン。『スマイル』もお蔵入りしノイローゼ状態に]
もし、あの時、ちょっと気持ちを変えて、出演していたら
(略)
[代わりに出演したのがオーティス・レディング]
スタックス・レコードの遺産を古い契約書を口実にすべて巻き上げたアトランティック・レコードのジェリー・ウェクスラー。彼はどんな顔をしてオーティスのステージを見ていたのだろう。モンタレーは「ヒッピー・ロックは金になることに気づいた音楽業界のモンスターたちがふところに契約書をしのばせて集まってきた最初の見本市でもあった」
(略)
[ジミヘンの]燃えたギターをこの時拾って持ち帰ったステージ・スタッフから受け継いだのはあのロスの怪人、フランク・ザッパだった。改造修理をして長く大事にしてステージやレコーディングでも使っていたとか……。
ギターの破片とか、そんなけちなものではなく、モンタレー・ポップの演奏をレコーディングしたウォリー・ハイダーらが手配したステージ・アンプを、すべてのプログラムが終了後こっそりと運び出して、近くのフェスティバル参加者の寝泊まり用のキャンプ・サイト(カレッジのフットボール場)で、フリーコンサートをやったのは、もちろんグレイトフル・デッドの面々。
ルー・アドラーは「グレイトフル(感謝するの意)どころか、最後までアングレイトフル、感謝などまるでない連中だった」と語っていた。
「モンタレー・ポップの成功の要因のひとつは、はじまりから終わりまで消えずに残ったこうした対立がもたらした緊張感にあっただろう」とサンフランシスコ・クロニクル紙の名物コラムニスト、ジョエル・セルヴィン
終焉
8月、夏の真っ盛りに春から引き延ばしにしていた夢の訪問を実現して、ジョージ・ハリソンは愛妻パティ・ボイドと連れ立って、この町にあらわれた。だが、極上のオーズリー・アシッドをきめて、パンハンドル公園を散歩していると、めざといファンに見つかり、気がつくとまわりは物珍しげに寄ってくるみすぼらしい格好の十代の若者たちがうろうろ、ぞろぞろ。わずか5ヶ月前にポールが見た光景とは似ても似つかないバッド・ヴァイヴの場所に変貌していた。遅すぎた!と気づいて、彼はそうそうに引き上げ、シスコを後にした。もう二度とアシッドはやらないと心に決めて。
秋が来て、ヒッピー見物の観光客たち、フィルモアのダンス・ライトショーでジェファーソンやデッド、ジミ・ヘンやクリーム、オーティス・レディングのステージを見て満足した若者たちの波が去ると、屑だらけのシスコの通りには、帰る家もリアリティも見失ったホームレス、ユースレス・ヒッピーたちのうつろな目が残った。最初にヒッピーを名乗り、創造的に新しい自分たちのライフスタイルを実現しようと動いてきた良質な人々は、6年の10月、「ヒッピーの葬儀」というイベントを催し、用意した棺桶にビーズやベル、バッジや花飾り、コスチューム、およそ本質とは関係のなかったこれまでの祭りの道具を投げこみ、それをかついで通りを行進すると、ゴールデン・ゲイト・パークで火をくべて、自分たちの手で現象としてのヒッピーを葬り去ってしまった。その中心メンバーだったロンとジェイのテーリン兄弟は本やポスター、店にあったすべてを欲しがる人たちにただで上げると店をたたみ、ならず者ジャーナリストを名乗り、ヘルズ・エンジェルスとヒッピーの間をとりもち、ハイト・ライフをさまざまなメディアに紹介してきたハンター・トンプソン、ディガーズのエメット・グローガン、ピーター・コヨーテ、といったロビン・フッドたちは、荷物をジープやトラックに積みこむと、東に北に南へと去っていった。
(略)
閉じられたサイケデリック・ショップの入り口にかけられた伝言板には、こんな言葉が残されていた。
「ムーヴメントはそれぞれの頭と手の中にある。ネヴァダはきみを必要としているかもしれない。ここを離れて、それぞれの新しい場所へ行け! 散れ! 転がり続けろ!」
(略)
そのメッセージに呼応するように、その秋、11月7日に登場した新雑誌で、21才の編集長は創刊の言葉をこう書いていた。「この新しい雑誌を世に贈る。雑誌の題はローリング・ストーン。
[ミック・ジャガー談]
「やばくてあやしい時代だったよ。アメリカはベトナム戦争で国中がまっぷたつになって騒然としてたし、フランスもパリの通りがデモ行進の人波でうまり、舗道がひっくりかえされて、石のつぶてが降っていただろ」
(略)
ジャガー/リチャーズがそんな動きを見過ごすわけがなかった。こうしてできたのが、タイトルもどんぴしゃ、ストーンズのソングカタログの中でも、もっとも政治的な歌といわれる「ストリート・ファイティング・マン」だった。「絶好の時に絶好な歌ができたって思ったのさ。そりゃ刺激されたよ、かたや眠ったようにおとなしいロンドン、なのにむこうは暴動とカーニバルが一緒になった騒ぎだったろ(笑)」
俺も王様をやっつけろって大声で叫んでみたいぜ
でもこの眠ったようなロンドンタウンでは
ストリート・ファイティング・マンの出る幕なんてありゃしないのさ
(略)
「なあにたいした曲じゃねえよ。歌詞だって曖昧だしな!」
キース・リチャーズは煙草の煙を吹き上げながら、相変わらずの怪気炎。(略)
「それなのにシカゴのラジオ局に行ったら、DJのやつ、暴動を始動する曲は流せませんなんてぬかしやがる。あまりにも破壊的な内容だからって。ああ破壊的だよ、ステージ観に来いよ、レコードより、もっと破壊的だからな!。そう言ったら、嬉しそうな顔して、コンサート会場に来て大喜びしてやがるんだ。あそこの町の連中は腐ってるぜ、まったく!」
(略)
[シングル発売]のわずか2日前には、シカゴ民主党大会の報道に集ったメディアの目の前で、全米からやってきたベトナム反戦のデモ隊がシカゴ市長の指示で、重装備で待ち受けていた警官隊、州兵に襲いかかられ、逮捕者多数、流血の大惨事。(略)4月のマーティン・ルーサー・キング牧師の暗殺。6月のロバート・ケネディ上院議員の暗殺事件
(略)
アメリカ各地のラジオ局は、シスコの進歩的FM局KSANなどをのぞき、その影響をおそれて、いっせいにこの曲の放送を自粛(略)
発売はされたものの「ストリート・ファイティング・マン」はヒット・チャートの40位にも届かなかった。(略)
[だがミックは]
「なあに、だいじょうぶさ。若い連中はかえって放送禁止なんかになると、喜んで飛びついてくるものさ。前に放送禁止にされた曲はミリオンセラーになったからね……」
今度もそのとおりになった。シングルも、年末に発売されたアルバムも100万枚を売り上げたのだ。
ウッドストック伝説
40万人の下水処理に出動したバキュームカーが、人波で会場を出られなくなり、仕方なく、シャベルカーで30メートルの溝を掘り、そこに流しこんだという。その丘の上には翌年、トウモロコシが大豊作だったとか……その伝説は本当だ。
フェスティバル後の世界
いったいあの頃どれだけの野外フェスティバルが行われたのだろう?(ウッドストック・フェスに先立つこと1週間、日本では第1回・中津川フォーク・ジャンボリーが開催されていた。これはちょっと誇らしい!)。ロンドンでは出所したあのホッパーが、ノッティングヒルのカリブ海系移民たちの野外フェスティバルを始めていた。
(略)
大きなヒッピー集会、反戦デモ、ゲイ解放行進には必ずその姿を見せる、あの髭の詩人アレン・ギンズバーグは、デモ学生たちを襲わないようにと、単身ヘルズ・エンジェルスの本部へ乗りこんで行き、“あのオカマのユダ公は度胸のある大した野郎だ!”とそのリーダー、ソニー・バーガーをうならせ、逮捕されては釈放、また逮捕……と忙しい日々を送っていた。
(略)
LSDの研究でティモシー・リアリーとともにハーバード大学を追われた学者、リチャード・アルパートがインドに旅してグルに会い、その覚醒的体験をババ・ラム・ダスの名で発表した「ビー・ヒア・ナウ」がベストセラーとなり、若者たちの関心はドラッグ・ハイから精神世界へ、インディアン文化や禅やインド哲学など、スピリチュアル・ワールドへとシフトしていた。イェール大法律学校の教授、チャールズ・ライクが、子供たちから大人世代が学ぶ。意識Ⅲという新しい意識伝達のスタイルが産まれていると、対抗世代を讃えた社会科学書『緑色革命』も世界中で大絶賛。グラハム・ナッシュがそれをわかりやすい言葉で歌にした「ティーチ・ユア・チルドレン」も映画『小さな恋のメロディ』に使われ世界的に大ヒットした。ちなみにこの頃、ゼミの教室に仲良く並んでライク教授の講義を受けていたのが、後に42代合衆国大統領になったビル・クリントンとヒラリーのふたり。
(略)
パンク女性詩人、パティ・スミスが感嘆の声をあげたのは(略)スターマン、デヴィッド・ボウイにも大きな影響を与えたビート世代の幻覚貴族作家、ウィリアム・バロウズだった。“ヘヴィーメタル”も“スティーリー・ダン”も彼の小説から生まれた名前。
(略)
「ドラッグの問題はドラッグそれ自体にあるのではない(略)
ドラッグをやって、いとも簡単に自分を失い、忘れてしまうような人間は、政府や官僚体制、権力のビッグ・マシーンがしかける意識コントロールの罠にも、たやすくはまってしまうだろう。ドラッグ問題の本質はそこにある、問題なのはそれを使う人間なのだ」
殺人事件が起こると火の粉がふりそそぐのを恐れ、後始末をツアー・マネージャーに押しつけ、翌朝すぐ逃げるようにロンドン行きの飛行機に乗ってとんずらを決めたストーンズ。ひとり孤立無援で後に残された彼、サム・カトラーはその後、救いの手を伸ばしてくれたジェリー・ガルシアたち、グレイトフル・デッドのマネージャーとなって活躍。
[関連記事]