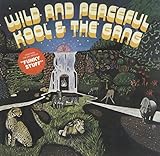前回の続き。
『Mumbo Jumbo』
こうして、ファンクは望ましいものとなった。が、それだけではなくっていた。実を言うと、アメリカ全土を感染させるほどの力があったのだ。イシュメイル・リードという作家が 1972年に『Mumbo Jumbo』という画期的な小説を出したが、これは、ぷんぷん臭う強烈なリズム感を持った黒人文化の本質と呼べるものが伝染病のようにアメリカに広がっていくという奇想天外な構想で書かれた、荒削りで汚穢趣味の小説だった。リードによって「ジェス・グルー」という名を与えられたファンキーな流行病は、ハイチ(略)からの最初の上陸地ニューオーリンズを(マルディ・グラで)大いに荒らした後、(1920年代のジャズの時代に)さらに北のセントルイスやシカゴへと広がり、第二次世界大戦前にビ・バップが生まれるのにちょうど合わせるようにしてニューヨークに攻めいっていくのだ。
リードは(マーク・トゥエインが読んだら卒倒してしまいそうな俗語をふんだんに使って)、謎に包まれた黒人の闇世界を再構築するという困難な過程を乗りこえ、当時主流となっていた黒人小説の手法を根底から覆した。黒人の生活や文化が、アメリカ白人の侵略を受けてばらばらに分断されてしまったため、黒人文学は、ずっと長きにわたって、そのことがいかに耐えがたいかということをもっぱら焦点にしてきた。が、リードはこの主題を180度転換し、アメリカを感染させる謎の現象であるジェス・グルーの持つ非情なまでの破壊性がけっして失われないのだということを明示してみせたのだった
(略)
リードによれば、黒人ダンス音楽が持っているリズミカルで官能的な本質がジェス・グルーなのであり、アメリカ白人は飽きることなくこのジェス・グルーを求めずにはいられないので、衰退していくというわけだ。
(略)
『Mumbo Jumbo』が象徴的な意味でもたらした衝撃は強力なものだったが、現実的な意味でもたらした衝撃も底の深いものだった。70年代後半に宇宙を舞台とする一大ファンク運動の仕掛人となったジョージ・クリントンは、発想の上で大いに参考になったと言って『Mumbo Jumbo』を絶賛している。ファンクが宇宙に広まるという構想をどうやって思いついたのかという質問を1985年に筆者がクリントンにしたときにしたときに、返ってきた答は「『Mumbo Jumbo』って読んだことあるか?」だった。
オハイオ・プレイヤーズ
1973年春まで、オハイオ・プレイヤーズと言えば、身体に鎖を巻きつけた坊主頭の黒人女性をアルバムのジャケットに載せている変態っぽいブルーズ・ロックのバンドという程度の認識しかされていなかったが、「Funky Worm」がラジオでかかった瞬間、その認識は完全に改められることとなった。変な「おばあちゃん」の語りやウォルター“ジュニー”モリスンの凄いキーボードのリフも耳を捉えるものがあったが、何よりも、ゆっくりと脈打ちながら揺れる振幅の大きなリズムが目立っていた。これは、それまでずっとゴッドファーザーの縄張りで、誰一人として足を踏み入れたことのない領域だった。
「Funky Worm」の発表でプレイヤーズの知名度は全国的なものとなり、キーボード奏者兼作曲者であるウォルター“ジュニー”モリスンの才能があまりにも光っていたため、ウェストバウンド・レコードは「ジュニー」単独で契約を交わし、オハイオ・プレイヤーズを手放した。その後オハイオ・プレイヤーズのほうは、1970年代半ばのファンクの音を決定づける重要バンドに成長するが、“ジュニー”モリスンは、きてれつで楽しいアルバムをウェストバウンドから次々と出し、ソロのアーティストとして名前を確立する。さらに、1977年にはPファンク軍団に参加して、「One Nation Under a Groove」、「Aqua-Boogie」、「(Not Just) KneeDeep」といったファンク史に残るヒットを共同生産した。
後にマーキュリー・レコードでオハイオ・プレイヤーズがヒットを連発するため、「Funky Worm」は影が薄くなって忘れられたも同然になるのだが、今日では、都会のぴりぴりした空気を描く鋭い音の代表として、西海岸ヒップ・ホップ界でさかんに再生されている。アイス・T、ドクター・ドレ、アイス・キューブ、N.W.A.らに見られる音数の少ない雰囲気を生み出した源の中心は、虫がくねくね這っている様子を表した「Funky Worm」の耳につくシンセサイザーなのだ。
クール&ザ・ギャング
玄関の外で赤ん坊達が泣いている
この上なく頼りなげに
夜の淑女が
きみの頭を自由にしてくれる
ゲットーで育って
木を1本も見たことがない
きみにこの歌詞が分からないのなら
きみと俺とで一緒に分かっていくようにしよう
クール&ザ・ギャング
「This is You, This is Me」(1973年)
クール&ザ・ギャングには、言いたいことが山ほどあり、演奏したい音楽も山ほどあった。「Heaven at Once」という曲は、ジャズの実験を試みている上に聞く者を考えさせる曲だが、歌詞に「『どうやって良くしていくの?』と言う子ども…。ほら、俺達は音の科学者。数字のように正確に演奏している」と言っている部分がある。クール&ザ・ギャングは活動が長くなっていくにつれ、常識外れの突拍子もない奇妙な試みを見せるようになるが、多彩な曲のどれをとっても、このグループ独特の理想主義、かっこいいスタイル、素晴らしい音楽性は光を放ちつづけていく。(現在はカリス・バイヤンと改名した) リーダーのロナルド・ベルは、このバンドが持っていた実験性について1974年にこう言っている「音楽的なを伸ばすために、いつも勉強している。それに、一緒にいるときには、色々な考えを試してばかりいる。うまくいく考えもあれば、駄目なものもあるけれど、とにかく考えを探すことに飽きたりはしないんだよ」。
Pファンク
やたらとメンバーの出入りがあったり、なかなか金銭の所在が明らかにならなかったり、責任者が判明しにくかったりしたせいで(略)大きな規模の混乱も生まれた。マネージャー/プロデューサーのロバート・ミドルマンは、Pファンク軍団に入った当初の「自分の仕事は、ギャラが出ない理由をミュージシャン達に説明することだった」と言っている。(略)
このような状況だったにもかかわらず、当時のPファンクによるアース・ツアーは一見の価値があるものだった。
(略)
オハイオ・プレイヤーズ、コモドアーズ、アース・ウィンド&ファイアの莫大な人気は白人にもおよんでいたが、Pファンクの場合、部外者の目には、ディスコ音楽とヴードゥー教がごっちゃになったようなものとしか映らなかった。カサブランカ・レコード重役のニール・ボガートとセシル・ホームズの支援を得たクリントンは、大胆にも、キッスやローリング・ストーンズといったロック・バンドの舞台装置を手がけた経験のあるジュールズ・フィッシャーという舞台デザイナーを使えるよう話をまとめた。(黒人音楽史上最高である) 275,000 ドルの予算で、パーラメントは(略)マザーシップを舞台に着陸させた。ニューヨーク州北部の空港にある飛行機格納庫で念入りなリハーサルがあった(略)
あらゆる点についてクリントンは途方もないことをやらかしてやろうと考えていて、みずから張りぼての車に乗ってピンプとして舞台に登場するところから始まり(略)バップ・ガンを持ったゲイリー・シャイダーが宙吊りになって飛ぶかと思うと、次から次へと大画面のアニメイションが登場したり衣装替えがあったり、最後には轟音をとどろかせてマザーシップが舞台に下りてくるといった具合だった。
(略)
Pファンク・ネタを使うことで有名な西海岸のラップ・スターの中には、当時アース・ツアーに行ってファンクのクローンとなった者が大勢いる。
(略)
興味深いのは、大成功まっただなかの1978年に、わざわざはクリントンはバンドを連れて「裏ツアー」を行っていて、大がかりな装置や衣装抜きの演奏を小さなクラブで行い(略)ひたすらジャム演奏に専念したということだ。ともかく、グループに綻び気配が見えてはいたものの、1980年のあいだは成功が持続した。
絶頂から崩壊へ
[「Flashlight」「One Nation Under a Groove」がR&B1位となり]
普通の音楽好きな連中までもが、パーラメントとファンカデリックについて怪しむようになっていた。あいつら何者なんだ?
(略)
[カサブランカは豪華付録&ジャケのアルバムを許可し]
『Motor Booty Affair』は、二つ折りのジャケットの内側に描いてあるアトランティス島の漫画が飛び出す絵本式に立てられるようになっていて、さらに多くのPファンク・キャラクターも切りぬいて立てられるようにしてあった。また、バービー人形で有名なマテル社が(ファンケンスタイン人形、ブーツィー人形、スター・チャイルド人形という)Pファンクの主要キャラクターの人形のセットを作ろうとして、実際に交渉も始まった。ただし、各キャラクターのイメージに関する権利と特許権使用料の点で同意に到らなかったため、この企画は却下された。とはいえ、どう見てもPファンクは凄かった。かなりのケチで通っているあのワーナー・ブラザーズさえもが[LP『One Nation Under a Groove』への7インチを付属を許可した](略)
驚異的な成功を収めるまで、Pファンクのメンバーは、旅も麻薬も愛情も、創造も演奏も生活も一緒にして、家族のようだった。ところが、成功と同時に、取り巻き連中、より強烈な麻薬、そして弁護士が現れるようになる。(略)
1981年頃には、内外から崩壊の動きが出て、グループは、強力な音楽を作ってラジオで生き残るための力を一気に失っていく。バンドの評判だけを売りにして誘われたメンバー達は、ギャラの支払いもないままツアー先や見知らぬ町で、お払い箱となった。
(略)
1978年という早い段階で既にグループを抜けたメンバーは、公然とジョージ・クリントンを非難する内容の音楽を作った。中でも一番怒りをあらわにしていたのは、脱退後にミューティニー(謀反/反乱)というグループを作ったジェローム・ブレイリーで、最初に出した力作『Mutiny on the Mamaship』はクリントの自分勝手さをとことん愚弄した内容だったが、ミューティニーのフォンクがP印であることは歴然としていた。
(略)
1982年にカサブランカが倒産してニール・ボガートが癌で死亡したことにより、最高に強力で気前のよい味方をクリントンは失ってしまう。また同じ頃、クリントンはワーナー・ブラザーズから何かと厄介なことを言われ[前 2 作が100万枚売れたのに、二枚組の予定だった『The Electric Spanking of War Babies』を一枚にされ、男根を描いたジャケットも修整させられた](略)
いっぽう、ブーツィーズ・ラバー・バンドも、1971年にカントリー・ロックをやっていた同名のグループがいるということで、「ラバー・バンド」の名称をめぐって降って湧いたような裁判沙汰に巻きこまれることとなった。そして、信じられないことに敗訴となったため、ブーツィーは所属先のワーナー・ブラザーズに対して275,000ドルの借金を負うこととなり(略)後に発表するアルバム収益は直接ワーナー側のものとなってしまった。この契約から解放されるまで5年待った 1988年に、ようやくブーツィーは個人名義のアルバム『What'spootsy Doin'』をコロムビア・レコードから発表する。
ほぼ一夜にしてパーラメントとファンカデリックを失い(、また同じくほぼ一夜にして流行遅れとなり)、Pファンクは急降下して地面にめりこんだ。(略)
[ロジャー・トラウトマンは]不吉な兆しを見てとり、ブーツィーとクリントンの力を得てザップのデビュー・アルバムを出せるところまでこぎつけてから脱走を遂げ、P印の財政危機をうまく回避して独自の超弩級ファンクを録音する。
「コカインが教会代わりになるまでコカインをやる」
ジョージ・クリントンは、伝統的な黒人キリスト教家庭に育っているものの、キリスト教への関心は薄かった。麻薬を体験したことによって信条が変わったのだそうで、「1963年にLSDをやるまで本気で宗教を信じてはいなかった。それまでは、十戒も耳に入ってこなかった」と語っている。極端な話、クリントンの使命は「コカインが教会代わりになるまでコカインをやる」ことだったのだ。クリントンは、精神的表現を身につけるために型破りな方法をとり、精神性とのあいだにある境界線をPファンクという手段によって──真の普遍救済論者として──とり除いたのだ。
ゴー・ゴー・バンド
トラブル・ファンク、E.U.、レア・エッセンス、レッズ&ザ・ボーイズ、そしてこれらのグループの師匠にあたるチャック・ブラウン&ザ・ソウル・サーチャーズといったゴー・ゴー・バンドは、一見やかましくて大所帯なだけのR&Bグループにしか見えないのだが、80年代最高に強力で熱くて本物の超弩級ファンクを演奏していた。ワシントンD.C.のクラブ・シーンでは、パーカッションを存分に駆使して1曲に2~3時間かけるのも当たり前というほどジャム演奏を延々続けるタイプの音楽が突如として盛りあがり、80年代初期、この種の音楽が演奏されていたのがD.C.にある (ブラック・ホールやコロシアムといった)ゴー・ゴー・クラブだったため、もっぱらゴー・ゴーという名で知られるようになった。
ゴー・ゴーのビートは、ハード・コアなファンクだ──厚みがあってゆったりしたベースのグルーヴがあり、さらにそのグルーヴに加えて、ティンバレスやコンガが情け容赦なくカウンター・パンチを浴びせてきたり、ホーンがジャズ風のブレイクをきめたりするかと思うと、観客も一緒に歌ったり、誰でも知っている有名なダンス・ヒットの歌詞やリフを使ったりという具合に、すべて荒削りな迫力があるものばかりで、ラジオでかかっている80年代R&Bのディジタル性をまっこうから否定するような音だった。ゴーゴーは、都会の黒いファンクが炸烈したビートを持っていたが、音楽に対する考え方という点では、むしろレゲエやカリプソやサルサといったアフロ・カリビアンのダンス音楽に見られるような延々と続くリズムと関連が大きい
(略)
ゴー・ゴーというビートを突き動かしていた最大の力は、コロンビア特別地区(District of Columbia) で苛酷な状況に取り巻かれている黒人社会(=ゴー・ゴーの聴衆)と連邦政府の重要機関である議事堂やホワイト・ハウスとが隣りあっているという強烈な皮肉だった。
(略)
ゴー・ゴー・ビートのゴッドファーザーは、1968年以来ソウル・サーチャーズというバンドを率いているチャック・ブラウンだ。疲れることを知らないブラウンは、際限なく続く単純でファンキーなグルーヴを確実に維持し、そのグルーヴを土台にして自由に遊んだり即興演奏をするという独特なR&Bを作りあげ、毎年々々クラブで数多くの演奏をこなして有名になっていった。「ずっとドラムの奴らには、あの独特なグルーヴをとにかく長く演奏させようとしてきた。あまりに単純なビートなんで、叩きたがらない奴がほとんどだ」と、ブラウンはジャーナリストのアダム・ホワイトに言っている。